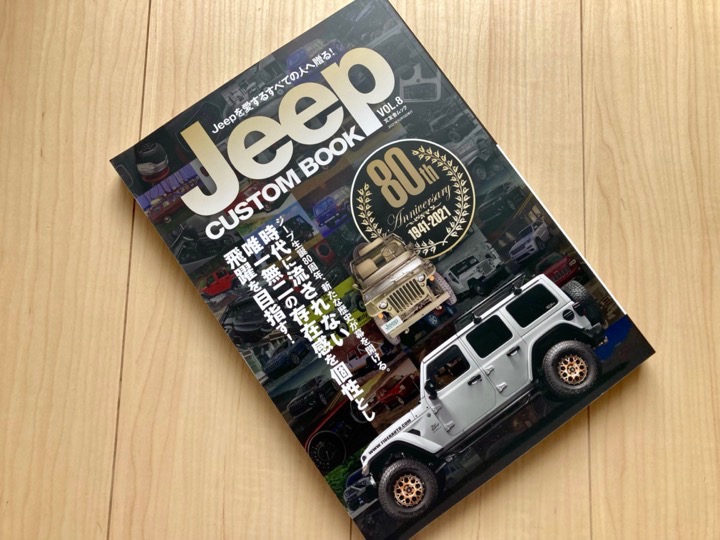#1829 やっぱりまとまりが良すぎて、ほかのモデルが見えてこない、三菱自動車・トライトン。

あらためて三菱のトライトンを振り返ってみましたが、すこぶる魅力のあるモデル、といった取りまとめができると思います。ボディサイズにしても、ベッドはそこそこの積載から、振る積載まで、そのカッコよさを十分に表現できますし、ステアリングフィールもまさにちょうどいい感じがありますし、リアタイヤがどこにあるのかとてもに分かりやすい。パートタイム式ではなく、フルタイム式を採用しているために、日常におけるドライビングにイージーさがありますし、いざとなったらリアデフロック機能も付いていますので、まさに、なんでもなりな状態となっていますので、まさに必要にして十二分かと思われます。もちろん、すべてが一新されたモデルとしては、強固になったラダーフレーム付きのモデルであり、そしてリアサスペンションはリジッド式を踏襲し、相変わらず縦置きスタイルな4WDシステム(フルタイム式搭載)を採用により、もはや、日常的な乗り味もまったく違っています。排気量がひとつ小さなディーゼルユニットを搭載しているところもいいですし、6速ATとの組み合わせもすばらしくいい。特に、過去にトライトンに乗っていたならば、乗り換えてまったく問題ないと思いますし、初めてトライトンにチャレンジするのであっても、このスタイリングに惚れ込んでいるならば、もはやオススメできる、かな、と思いました。 ただですね、いわゆるヘビーデューティ系な4WDですので、意外に取り回しがいい、思ったよりもハンドリングが素晴らしいと思っても、やっぱり、ラダーフレーム付きモデルであって、その車両重量は2080kgから、となりますので……。その 一方で、自分で買うか、と、問われると、気が引けるというところもあり、わりとベタぼれなんだけど、サイズ的だけではなく、重量のほうが難しいや、という面もあったりします。それにしても、やっぱり、ピックアップトラックというスタイルは今の自分には当てはまらないことが正直なところで、さらにルーフレスなベッドの使いように何も当てはまることがなかったりもします。実は歳を取ってくれると、デカイクルマが好きでなくなる方向性も生まれてきまして、もはや、3ドアでいいんじゃないか、って思えてきますな。